| 後期高齢者医療制度 | 後期高齢者医療制度に加入する方 | 届出について | 後期高齢者医療制度で受けられる給付 | 保険料について |
後期高齢者医療制度
平成20年4月より、従来の老人保健制度が廃止され、後期高齢者医療制度が創設されました。
これにより、75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上)の方は、お住まいの都道府県ごとに設置された広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することになりました。
なお、保険料の徴収や各種窓口業務については、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口が行っています。
後期高齢者医療制度に加入する方
後期高齢者医療制度に加入する方は、以下の方々になります。
届出について
次のような場合は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口に届出をしてください。
後期高齢者医療制度に加入する
- 他の都道府県から転入してきたとき
- 65歳から74歳までの方のうち一定の障害がある方で、申請により加入するとき
- 適用除外の要件に該当しなくなった(生活保護の廃止など)75歳以上の方が加入するとき
※75歳の誕生日をむかえることによって後期高齢者医療に加入される場合は、窓口への届出などといった、特段の手続は必要ありません。
後期高齢者医療制度から脱退する
- 他の都道府県へ転出されるとき
- 後期高齢者医療の加入者が死亡したとき
- 65歳から74歳までの方のうち、一定の障害があることが認定され、後期高齢者医療に加入していた方が、一定の障害の状態に該当しなくなったとき
- 適用除外の要件に該当(生活保護の開始など)したとき
持参するものについては、事前にお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。
後期高齢者医療制度で受けられる給付
加入している方が病気やケガで病院にかかったり、死亡されたときには、治療など(療養の給付など)や現金の給付(療養費の支給)が受けられます。
これを「保険給付」といいます。
基本的な給付の内容は、これまでに加入されていた医療保険(職場の健康保険や国民健康保険など)と同じです。
①病院などにかかるとき(療養の給付)
病気やケガで病院などにかかるとき、窓口でマイナ保険証や資格確認書を提示することにより、医療費の一部を負担する(一部負担金)だけで診療を受けることができます。
一部負担金以外の医療費は、後で後期高齢者医療広域連合より医療機関等に支払われます。
なお、病院などの窓口で支払っていただく一部負担金の割合(自己負担割合)は、所得によって異なります。
| 区分 | 自己負担 | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 (※1) | 3割 | |
| 一定数以上の所得(※2)がある方 | 2割 | |
| 一般 | 1割 | |
| 住民税非課税世帯 | 低所得Ⅱ (低所得Ⅰ以外の方) |
|
| 低所得Ⅰ | ||
※1 同じ世帯内に課税所得が145万円以上となる加入者(被保険者)がいる方をさします。
ただし、条件により1割又は2割の区分になる場合があります。
詳しくはお住まいの市区町村の後期高齢者担当窓口にお尋ねください。
※2 課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、
複数世帯の場合合計320万円以上。
②入院したときの食事代
入院中の食事代については、診療や薬にかかる費用とは別に、一部を自己負担します。
残りは後期高齢者医療が負担します。
入院時の食事代(1食当たり)の負担額は次のとおりです。
| 1食当たりの食費 | |||
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 510円 | ||
| 一般 | |||
| 住民税非課税世帯 | 低所得Ⅱ | 90日以内の入院 | 240円 |
| 90日を超える入院 | 190円 | ||
| 低所得Ⅰ | 110円 | ||
※「現役並み所得者・一般」には、自己負担額が2割となる方を含みます。
療養病床に入院したときの食事代
療養病床に入院する場合には、食費・居住費を負担します。負担額は次のとおりです。
| 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) | ||
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 510円 (一部の病院では、470円の場合もあります。) |
370円 | |
| 一般 | |||
| 低所得Ⅱ | 240円 | 370円 | |
| 低所得Ⅰ | 年金額が80万円以下の方など | 140円 | 370円 |
| 老齢福祉年金を受給している方 | 110円 | 0円 | |
※「現役並み所得者・一般」には、自己負担額が2割となる方を含みます。
③いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)
次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口に申請をし、支給決定されれば、自己負担分を除いた金額が支払われます。
| 医療の内容 | 急病などやむをえない事情で、保険の取扱いをしていない病院で治療を受けたときや、 マイナ保険証や資格確認書を提示せずに治療をうけたとき |
|---|---|
| 後期高齢者医療を扱っていない柔道整復師の施術代(骨折・捻挫・脱臼など) | |
| ★医師から指示された、はり・きゅう・あんま・マッサージ代 | |
| ★治療用装具(コルセット、義足など)を購入したとき | |
| ★輸血のための生血代 | |
| 海外渡航中に急病やケガで病院にかかったとき(海外療養費) |
★の付いた項目は、医師が認めた場合に適用されます
④亡くなられたとき(葬祭費)
加入者(被保険者)が亡くなった場合、葬儀を執り行った方に葬祭費が支給されます。
金額等については、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。
⑤移送されたとき(移送費)
病気やケガなどで歩行が困難な方で、医師の指示により治療上必要であり、緊急でやむをえず別の病院に移送したときなどに、移送に要した額が支給される場合があります。
⑥交通事故にあったとき
交通事故などの第三者の行為によりケガをした場合の治療費は、本来は加害者が負担すべきものですが、状況によりマイナ保険証や資格確認書を使って診療を受けることができます。
マイナ保険証や資格確認書を使って治療をする場合は、必ずお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口に届出をしてください。
※示談により後期高齢者医療が使えなくなる場合がありますので、その前に必ず窓口に連絡・届出をしてください。
⑦医療費が高額になったとき(高額療養費)
1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。
ただし、入院中の食事代や保険がきかない差額ベッド代、歯科の自由診療などは対象になりません。
限度額は、所得区分によって異なります(下表参照)。
- 外来分は被保険者一人ひとりの計算ですが、入院がある場合には、世帯単位での計算(外来もある場合は外来分+入院分)になります。
- 現役並み所得者は、過去12ヶ月間(1年間)に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が変わります(下表参照)。
| 区 分 | 外来(個人ごと)の 自己負担限度額 |
入院及び世帯の 自己負担限度額 |
||
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得Ⅲ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回該当:140,100円) |
|||
| 現役並み所得Ⅱ 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回該当:93,000円) |
|||
| 現役並み所得Ⅰ 課税所得145万円以上かつ、 基準収入額が単身383万円 (世帯は520万円)以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回該当:44,400円) |
|||
| 一般 課税所得145万円未満 |
18,000円 (年144,000円) |
57,600円 (44,400円) |
||
| 低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ||
| 低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | ||
高額療養費の申請について
高額療養費の申請は、初回のみ必要となります。初めて高額療養費に該当されたときには、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口に申請をしてください。
高額医療・高額介護合算療養費
年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、年間の限度額を超えた場合には、申請により超えた分が高額介護合算療養費として後から支給されます。
詳しくはお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にお尋ねください。
保険料について
後期高齢者医療と保険料
後期高齢者医療の加入者の皆さまが病気やけがをしたときの医療費などの支払いにあてる費用の一部として、加入者一人ひとりから保険料を納めていただくようになります。
保険料は、国や県、市区町村からの公費及び他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となっています。
保険料の軽減
所得の状況などにより、保険料の軽減を受けられる措置があります。
詳しくはお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にお尋ねください。
低所得世帯に対する軽減措置
世帯の所得に応じて軽減措置が受けられる場合があります。
詳しくはお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。
被用者保険(※)の被扶養者に対する軽減措置
後期高齢者医療制度へ加入する前日まで被用者保険(※)の被扶養者だった方は、保険料が軽減されます。
詳しくはお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にお尋ねください。
※被用者保険とは、会社などに勤めている方が加入している健康保険のことです。国民健康保険、国保組合は含まれません。
保険料の納付が困難なとき
保険料の納付が困難な場合は、そのままにせず、お早めにお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。
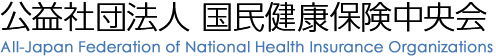
※生活保護を受給されている方など、適用除外の要件に該当するときは、後期高齢者医療制度には加入しません。